
BONDS
Thank you -サンキュー-
¥49,000
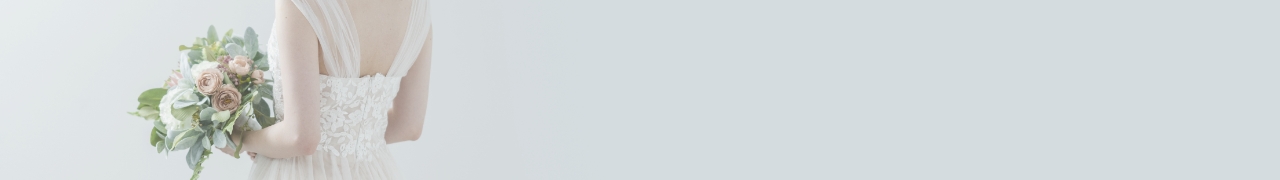
ブライダルノート
Together

結婚にかかる費用がいくら必要なのかわからないと、目標額を決めづらいもの。もちろん、貯金は多いに越したことはありませんが、具体的にどのくらい必要なのかを押さえておくようにしましょう。
そこで今回は、結婚費用の総額とそれぞれの内訳、結婚費用を貯金する方法、足りない場合の解決策などをご紹介します。スムーズに結婚準備を進めて充実した新生活を送るためにも、ぜひご参考にしてください。

結婚にかかる費用は、婚約指輪や結婚指輪、結婚式だけでなく、新婚旅行や新生活などもあります。ここでは、「ゼクシィ結婚トレンド調査2023(全国(推計値))」から、結婚にかかるそれぞれの費用をご紹介します。
「同調査」によると、結納・婚約〜新婚旅行にまつわる結婚費用の平均総額は415.7万円です。内訳を見ると400〜500万円未満が23%ともっとも多く、次いで300〜400万円未満・200〜300万円未満が同率で16.7%、500〜600万円未満が15.2%という結果になっています。
それでは、各項目ごとにかかった費用の平均を見ていきましょう。
先輩カップルが婚約指輪にかけた費用の平均金額は38.2万円です。内訳を見ると30〜40万円未満が31.4%ともっとも多く、次いで20〜30万円未満が17.7%、50〜60万円未満が15.9%、40〜50万円未満が11.1%という結果になっています。
この結果から、半数以上のカップルが婚約指輪に30〜60万円の費用をかけていることがわかります。
食事を含めた結納式にかかった費用の平均金額は20.6万円です。内訳を見ると、5〜10万円未満が23.8%ともっとも多く、次いで10〜15万円未満が20.4%、5万円未満が12.4%という結果になってます。
一方、顔合わせ食事会にかかった費用の平均金額は6.7万円です。内訳を見ると、5〜10万円未満が43%ともっとも多く、次いで5万円未満が29.6%、10〜15万円未満が15.6%という結果になっています。
結納式に比べると、顔合わせ食事会のほうが費用を抑えることが可能です。とはいえ、両家の親睦を深める大事な機会になるので、費用面だけで決めずにお互いの両親に相談して決めるとよいでしょう。
先輩カップルが結婚指輪の購入にかけた平均金額は28.1万円です。なかでも多かったのが20〜25万円未満で28.3%、次いで25〜30万円未満が19%、30〜35万円未満が16.9%と続いています。
結婚指輪はリーズナブルなものから高額なものまで価格が幅広いため、2人の好みに合った指輪を購入するとよいでしょう。
なお、結婚指輪については以下の記事でもご紹介しているので、ぜひご参考にしてください。
30代の結婚指輪(マリッジリング)の相場は?20代との金額差もご紹介
先輩カップルが結婚式にかけた費用の平均金額は、挙式・披露宴・ウエディングパーティー合わせて327.1万円です。なかでも、400〜450万円未満が14.5%ともっとも多く、次いで300〜350万円未満が13.7%、350〜400万円未満が11.4%と続いています。
結婚式は、式場や挙式スタイル、ゲストの人数などによって費用が異なるため、上記のデータはあくまでも参考程度に捉えておきましょう。
先輩カップルが新婚旅行にかけた平均費用は、お土産代を除く2人分の旅行費用のみで43.4万円でした。とくに多かったのが20〜30万円未満で18.7%、次いで10〜20万円未満で17.3%、30〜40万円で16.7%となっています。
新婚旅行は行き先が国内・海外によっても費用が大きく異なりますし、宿泊日数や宿泊先によっても変わります。そのため、必ずしも上記の費用がかかるとは限りません。あくまでも参考程度に捉えておくとよいでしょう。
結婚を機に新生活を始める場合は、引っ越し費用や新居の契約金、家具家電の購入費などがかかります。「新婚生活実態調査2023(リクルートブライダル総研調べ)」によると、新生活に欠かせないインテリアや家具の購入平均金額は24.4万円、家電製品の購入平均金額は28.8万円となっています。
また、新婚家庭の79.9%がインテリアや家具の「支出あり」または「支出予定あり」と回答し、77.8%が家電製品の「支出あり」または「支出予定あり」と回答していることから、結婚を機に家具家電を購入する方がほとんどであることがわかるでしょう。
ただし、すでに同棲している場合やどちらかの家に住む場合はこの限りではありません。
なお、結婚に向けて必要な準備や結婚指輪を選ぶ際のポイントについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。併せてご確認ください。
プロポーズの後に入籍、結婚にむけて必要な準備
結婚指輪の相場ってふたりでいくら?値段以外に重視すべきポイントとは?

結婚のために貯金をするなら、計画的に行うことが大切です。「どのような結婚式を挙げたいか」「新婚旅行はどこに行きたいのか」など2人の希望を話し合うことで、より貯金に対して積極的になれるかもしれません。以下のような貯金方法があるため、ぜひご参考にしてみてください。
できるだけ短期間で効率的に貯金するためにも、毎月の出費に無駄なものがないかを見直して節約を心掛けましょう。
そのためにも、まずは家計簿をつけて収支の状況を確認してください。しっかりと記録することで、日々の無駄遣いがひと目でわかります。
次にスマホ代や保険代などの固定費に無駄がないかを確認しましょう。
具体的な方法としては、格安スマホにする、課金制の不要なサービスを解約する、保険の見直しをする、同棲して家賃を抑えるなどです。光熱費や交際費もある程度節約することは大切ですが、やりすぎるとストレスになってしまうため、無理のない範囲にしておきましょう。
普段使っている給与口座や生活費用の口座とは別に積立用口座を作り、毎月決まった額を入れる方法もあります。
生活して余ったお金を貯蓄に回す方法だと無駄遣いをしてしまいがちなので、給料日になったらまずは積立用口座へ決まった金額を入れる先取り貯金がおすすめです。そうすると残った金額でやりくりをしなければいけなくなるため、自然と無駄遣いが減ります。
貯蓄方法としては、お互いに目標額を決めて別々に積み立てをしていくパターンと、同じ口座に積み立てていくパターンがあります。
どちらの場合もキャッシュカードを作らず入金するだけと決めておくことで、簡単には引き出しができなくなりますし、貯蓄額も把握しやすくなるでしょう。
最初に目標額と期日を決めておくことで、毎月どれくらいの額を貯蓄に回せばよいのかがわかります。
キャッシュレス決済やポイントカードの活用で、ポイント還元が受けられるサービスも増えています。
「現金が手元になくても使えるため無駄遣いしてしまいそう」という方もいますが、しっかりと家計簿をつけて収支の状況を把握しておけば問題ありません。
1回あたりに貯まるポイントはわずかでも、コツコツと貯めてそれを使うことで支出を抑えることができるでしょう。
キャッシュレス決済やポイントカードは結婚後も使えるので、結婚費用の準備段階から活用しておくとよいかもしれません。

頑張って貯金をしたつもりでも、「目標額に届かなかった」ということもあるでしょう。そのような場合は、以下の方法で解決できるかもしれません。もし貯金が足りずお困りの場合は、ぜひご参考にしてみてください。
結婚式ではご祝儀をいただくため、ご祝儀でマイナス分を賄う方法もあります。
結婚式の形式や参列者の人数などにより異なりますが、「ゼクシィ結婚トレンド調査2023(全国推計値)」によると、ご祝儀総額の平均は197.8万円です。
なかでも200〜250万円未満が19.7%ともっとも多く、次いで150〜200万円未満が17.6%、100〜150万円未満が16.5%という結果になっています。
さらに細かく見てみると、招待客1人あたりのご祝儀額は親族から平均7.4万円、上司からは平均4.2万円、恩師からは平均4.1万円、友人からは平均3万円という結果になっています。
しかしなかには、親族から10万円以上のご祝儀をいただいたと回答した方が27.3%、上司から5万円以上のご祝儀をいただいたと回答した方が46.8%もいるため、ゲストとの関係性によってもご祝儀総額は変わってくるといえるでしょう。
ただし、ご祝儀は結婚式当日にゲストからいただくものということは忘れてはいけません。
もし結婚式の費用をご祝儀で賄いたいと考えている場合は、結婚式場に支払いのタイミングを確認しておきましょう。
結婚するとなると親から援助をしてもらう人も多いようです。
実際に「ゼクシィ結婚トレンド調査2023」によると、結婚費用に対して親や親族から援助があったと回答したのは78.7%です。援助総額の平均は181.1万円となっていて、内訳としては100〜200万円未満が35.7%ともっとも多く、次いで200〜300万円が27.3%、100万円未満が18.5%となっています。
このことから、多くのカップルが金銭的な援助を受けていることがわかります。そのため、「必ず2人だけで賄う」と考えすぎず、両家へ相談してみるのもよいかもしれません。
ただし、親や親族から援助してもらう際には贈与税に注意しましょう。
そもそも贈与税とは、個人から財産をもらった際にかかる税金のことです。基礎控除額は年間110万円までとなっており、この金額内であれば非課税であるため問題ありませんが、もし110万円以上になる場合は贈与税の対象になることも。
しかし、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用することで1人あたり300万円までの贈与が非課税となり、税金が控除されます。
活用する際にはいくつかの条件を満たす必要がありますが、親や親族からの援助を受ける場合には利用を検討してみるとよいかもしれません。
結婚資金が足りない場合、結婚式や新婚旅行などの各種費用を抑えるという方法もあります。
たとえば、結納式を顔合わせ食事会に変更することで支出を抑えることができますし、結婚式の会場や時期を変更するだけでも費用を抑えることができます。
とくに結婚式では、お金をかけるところと手作りをしてお金をかけないところをしっかりと分ければ、総額を抑えることが可能です。
また、新婚旅行の行き先として海外を検討しているのなら、比較的費用が抑えられるアジア圏内や国内へ変更するのもよいでしょう。ホテルのランクを下げる、飛行機は格安航空会社を使うというのも一案です。
ただし、多くの方にとって結婚に関するイベントは人生で一度きりなので、「費用を抑えすぎて後悔した」ということにならないように注意しましょう。
銀行などで借り入れができるフリーローンやブライダルローンを活用するのも一案です。
ブライダルローンとは、結婚にかかわることのみに活用できるローンのこと。婚約指輪や結婚指輪、結婚式、新婚旅行などの費用として使えます。
結婚後の出費が増える・一般的なローンと比較すると提出書類が多く融資までに時間がかかるというデメリットもありますが、結婚にかかわることにしか使えないため借りすぎを防げるというのは大きなメリットといえるでしょう。
「結婚式では衣装や演出にこだわりたい」「新婚旅行は海外に行きたい」という希望も叶えられるかもしれません。
なお、ブライダルローンについては以下の記事で詳しくご紹介しています。2人の貯金や両家からの援助だけでは賄いきれずブライダルローンの利用を検討している方は、ぜひご参考にしてください。
ブライダルローンってなに?メリット・デメリットや申し込みの流れ

結婚する場合、婚約指輪や結婚指輪の購入、引っ越し、家具家電の購入、結婚式、新婚旅行などさまざまなことに費用がかかります。
結婚指輪にかける予算や結婚式の規模、新婚旅行の行き先などを大まかに決めることで、目標金額と毎月の貯金額が明確になり、より貯金しやすくなるでしょう。まずは2人でよく話し合い、目標金額を設定することをおすすめします。
また、結婚費用として親や親族から援助を受けたと回答した先輩カップルは半数以上いたため、無理に2人だけで賄おうとせずに両家へ相談してみるのもよいかもしれません。
関連記事

Together
2023.10.12

Together
2023.10.26

Together
2022.08.06

Together
2022.03.30
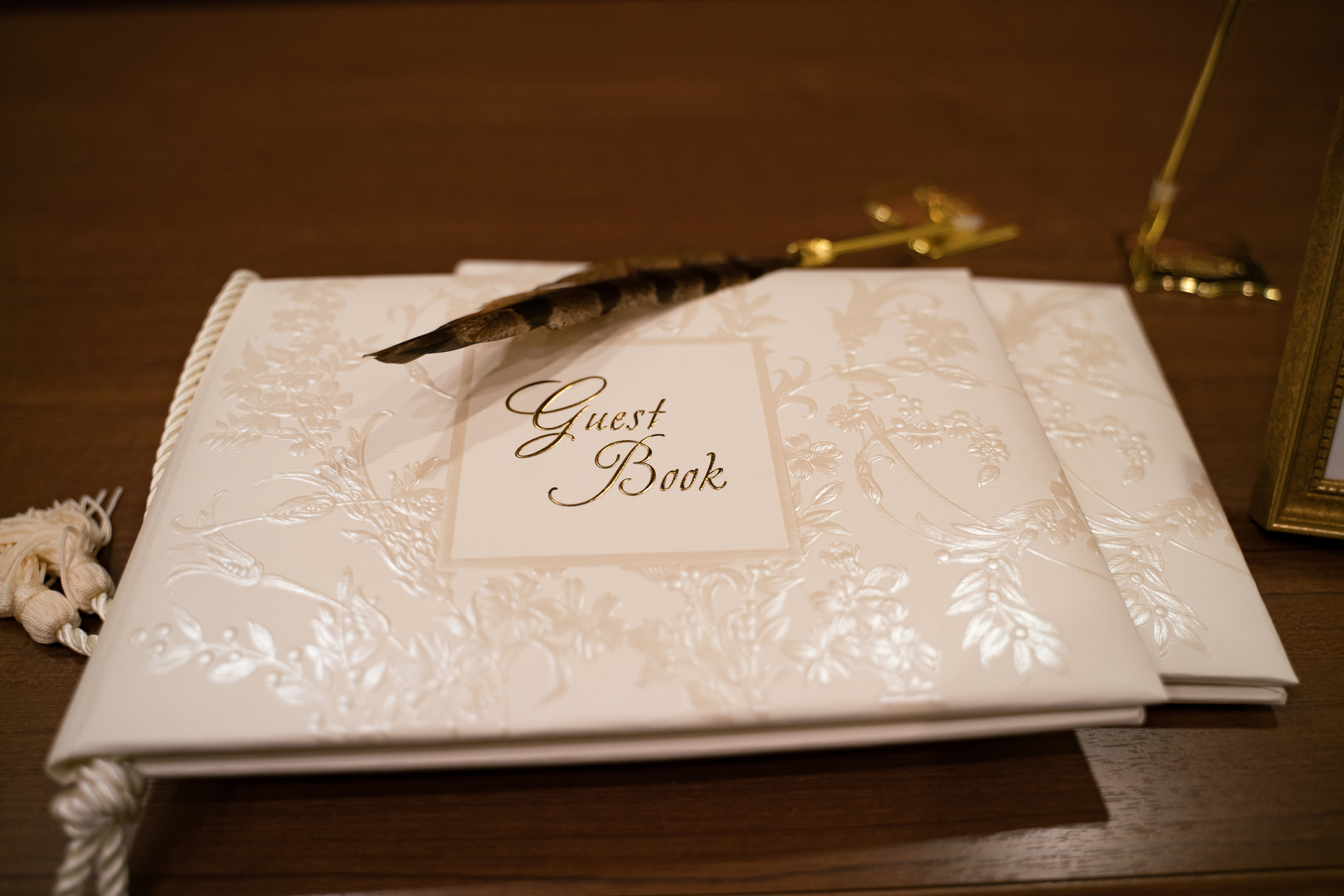
Together
2021.12.01

Together
2021.07.30